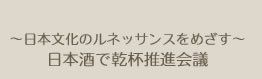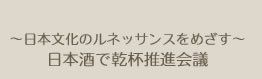|
酒と薬用
江戸時代の人は、酒を健康づくり、体づくりにも大いに利用していた。飲み過ぎれば万病のもととはなるが、上手に使えぱ百薬の長となることをよく知っていたのだ。
十返舎一九作『東海道中膝栗毛』の第五編上巻に四日市の旅籠屋(はたごや)での弥次郎兵衛と喜多八の出来事が面白く語られている。弥次さんが風呂に入って留守で、喜多さんが部屋で一服していると、酒売り商人が酒をかついで売りに来る。喜多八「おっと、その焼酎(しょうちゅう)を少しくんな」と茶わんに注がせて銭を払い、その焼酎を足に吹きかけて「よしよし、これでくたぴれが休まるだろう」という条がある。
つまり旅の疲れを取るために焼酎を足にかけているのだ。このことは、当時焼酎がかなり普遍的に普及していたことと、そして焼酎は疲れを取るということがかなり一般大衆にまで広まっていたことを物語っている。
今と違って医学が進歩しておらず、民間伝承療法や民間医療が主体だった時代、酒はそれらの療法の媒体として大変重宝されていた。その代表的例が薬用酒だった。
例えぱ江戸時代に人気の薬用酒といえぱ備後(今の広島県東部)や尾張知多郡大野村でつくられた「保命酒」で、『守貞漫稿』には「薬用銘酒は備後鞆(とも)の保命酒」とあり、また『尾張名所図会』には、「保命酒、知多郡大野村。其美味他の名酒と呼ぶものの類にあらず、実に一飲して長命を保つべし」とある。焼酎に白糖を多く加え、それに桂皮(けいひ)、茴香(ういきょう)、当帰、地黄、甘草、人参などの薬草根を浸してつくった強壮酒だ。信州伊那谷の天竜川に沿った中川村で生まれたのが「養命酒」で、これは今日まで続いてきている。
肥後や阿波、丹波などでつくられていた「桑酒(くわさけ)」は桑の実の汁と砂糖を焼酎に混ぜてつくった紫色の薬酒で、『本朝食鑑』には「桑酒、中風や五瘴、脚気及ひ疾嗽(しつそう)を治す」とある。ほかに「梅酒」「延命酒」「菊花酒」「クコ酒」「地黄酒」「長命酒」などが人気であった。
「医」の旧字体に当たる「醫」という字は「殹」と「酉」の会意文字で「酉」は申すに及ぱず酒または酒壺のこと、「殹」は「薬草を封じ込む」の意で、すなわち「酒壺に薬草を封じ込み薬酒を醸す」ことである。当時の医者というのは、そういうように酒を使った薬の処方まで担っていたのであった。
パスツールを超えた日本人
フランスの著名な微生物学者パスツールが、市場に出されたワインが腐敗するのを防ぐため、低温殺菌法を行ったのは一八六〇年代であった。ところが、それより三百年も前の一五六〇年代に、奈良の興福寺の僧りょたちはパスツールとまったく同じ方法で日本酒を低温殺菌(火入れ)していた。『多聞院日記』や『御酒之日記』といった、当時の僧りょらが書いた酒造りの作業日記に明記されている。
例えぱ「酒ニサセ了、初度」(永禄十二年=一五六九)とあり、これは「酒を煮て終わる。初めて煮るなり」ということで、「火入れをしたが、これが一回目」ということを言っている。一回火入れをした酒を、念のために二度、三度と火入れをしたことも記されている。
さて、最大のミステリーは、当時は温度計などなかったのに、どうして目的の火入れ温度(大体五十五度で五分から十分くらい。現代の低温殺菌も、この目安である)を知ったのか?ということ。さすがに昔の人たちは知恵が深い。温度計などなくても、ちゃんと目的の温度を知る方法を考えついていたのである。「御酒之日記」には次のような記述があるのだ。
「酒の煮方は四月二十五日ころには飲み燗ぐらいの温度に、五月二十五日ころには手引き燗ぐらいの温度にして、上に浮く泡をよく取ること。六月二十五日ころは、飲み燗に比べてもっと熱く煮てから、撙に戻しておよそ七日問はふたで口を包み、決して息(蒸気のこと)を出してはいけない。こうすることによりおかわり時(一年後)まで酒の変質はない」
当時は酒は燗をして飲んでいたので、その燗の温度をもって火入れの温度を説明していたのである。「飲み燗」は今でも大体四十度ぐらい、「手引き燗」は酒に指を入れて「熱い」と言って手を引っ込める温度で大体四十五度ぐらい。日記には、さらに温度を上げて「上に出る泡が多くなったら(熱火あつび)それを取り去るとある。実は実験で分かったことだが、昔のように雑味成分の多い酒は、熱を加えていくと五十五度から六十度になると泡が発生してくるのである。この泡立つあたりを火入れ温度の限界としていたようで、火入れ温度を「飲み燗」(薄火)、「手引き燗」(中火)、「泡立ち燗」(熱火)というように表現していたのであった。いつの世でも、ものが不自由なほど知恵は生まれる。
|